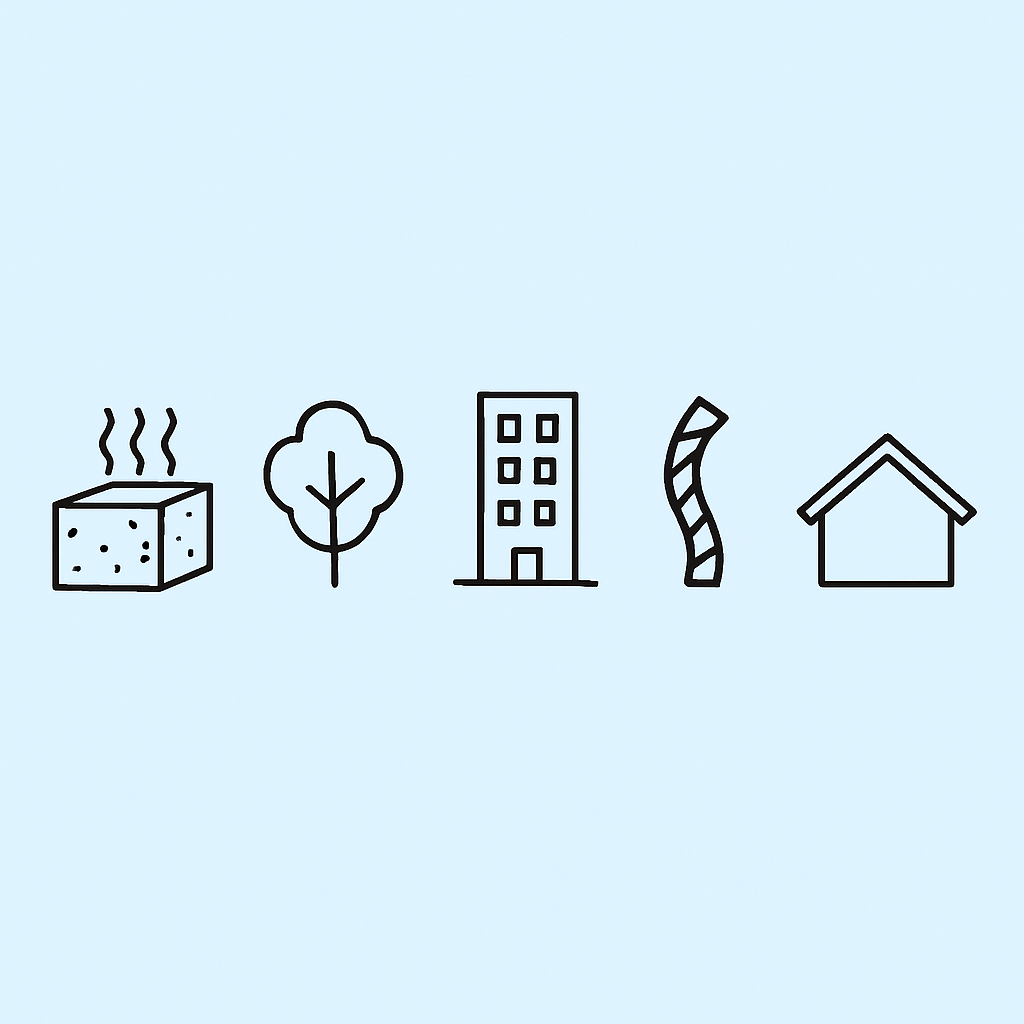
コンクリートは「止まらない」材料
コンクリートはセメントと水の化学反応(水和反応)で硬化します。
JIS規格や設計基準では「28日養生」で強度を確認しますが、実は反応はその後も続きます。条件によっては数十年後も内部で反応が進み、強度が微増することもあります。
一般住宅でも、施工後しばらくは内部の水分移動や乾燥収縮が進むため、基礎や土間のひび割れ抑制には十分な養生期間が大切です。
木材は今も「呼吸」している
製材後の木材も、湿度変化で水分を吸ったり吐いたりします。
このため、夏は膨張し、冬は乾燥して縮む現象が起こります。
例えば無垢フローリングでは、冬場に隙間ができ、梅雨時にはほぼ閉じることが多いです。
設計や施工では、伸縮を見越したクリアランスを設けることが重要です。
超高層ビルは「揺れるように設計」されている
地震や強風に対して、ビルが全く揺れないようにすると構造材に過剰な力がかかり破損のリスクが高まります。
そのため、制振ダンパーや免震装置を組み込み、揺れを適度に逃がす構造が採用されます。
最近では、チューンド・マス・ダンパー(TMD)と呼ばれる巨大なおもりを高層階に設置し、揺れを打ち消す方式も普及しています。
鉄筋の「サビ」は全てが悪ではない
鉄筋はアルカリ性のコンクリートに覆われることで、パッシブフィルムという酸化皮膜に守られています。
施工中に表面がうっすら赤茶色になることがありますが、これは表面酸化であり、構造耐力に直ちに影響するとは限りません。
ただし、深部まで腐食が進むと断面欠損となり危険です。現場では、許容範囲のサビかどうかを的確に判断することが求められます。
屋根勾配は「気候と文化の産物」
日本の瓦屋根は台風や豪雨を考慮し急勾配が多く、北欧では雪下ろしのためさらに急勾配、地中海沿岸は乾燥気候でほぼフラット。
近年はデザイン性や太陽光パネル設置効率を考え、緩勾配の金属屋根も増えています。
勾配は単なる雨仕舞のためだけでなく、地域の景観・文化的背景と密接に関わっています。
まとめ
建築は「見えない工夫」と「長年の知恵」の積み重ねで成り立っています。
素材や構造の性質を理解することで、家づくりやリフォームの判断もより的確になります。
もし新築や改修を計画しているなら、これらの知識はきっと役立つはずです。


コメント
zfwmtmundnqjjsmfxvqjztwzozgolu